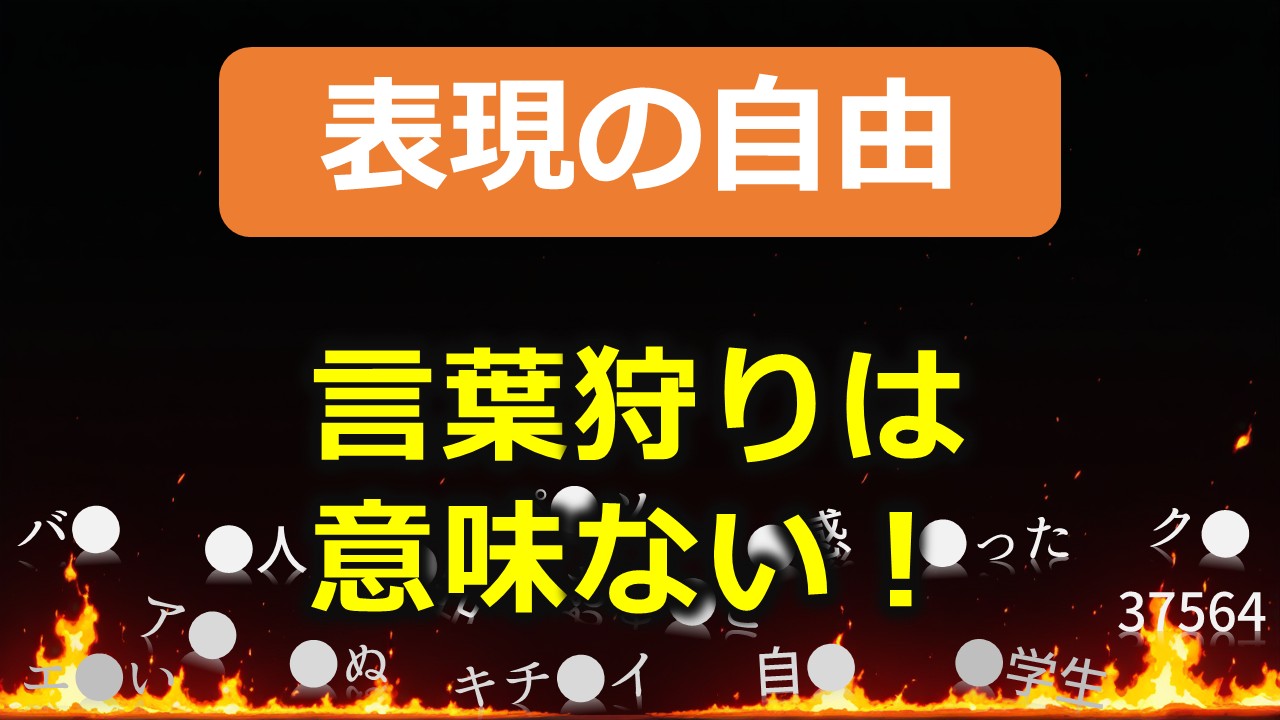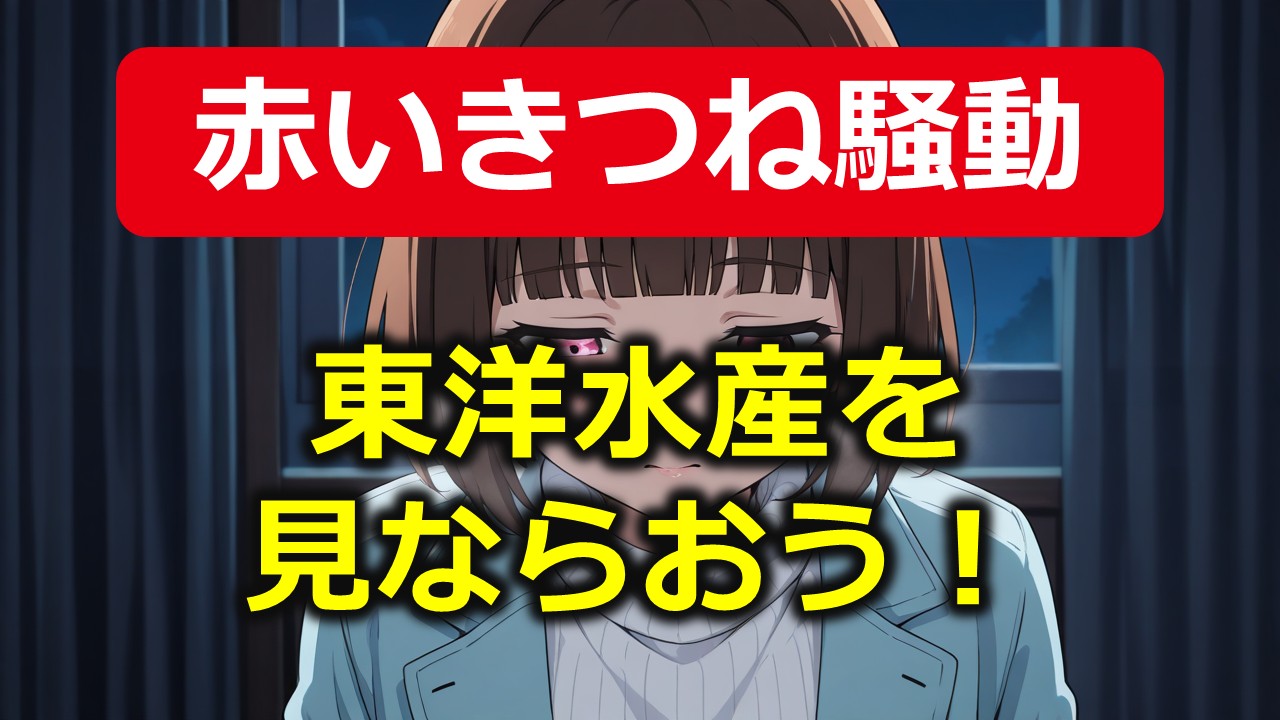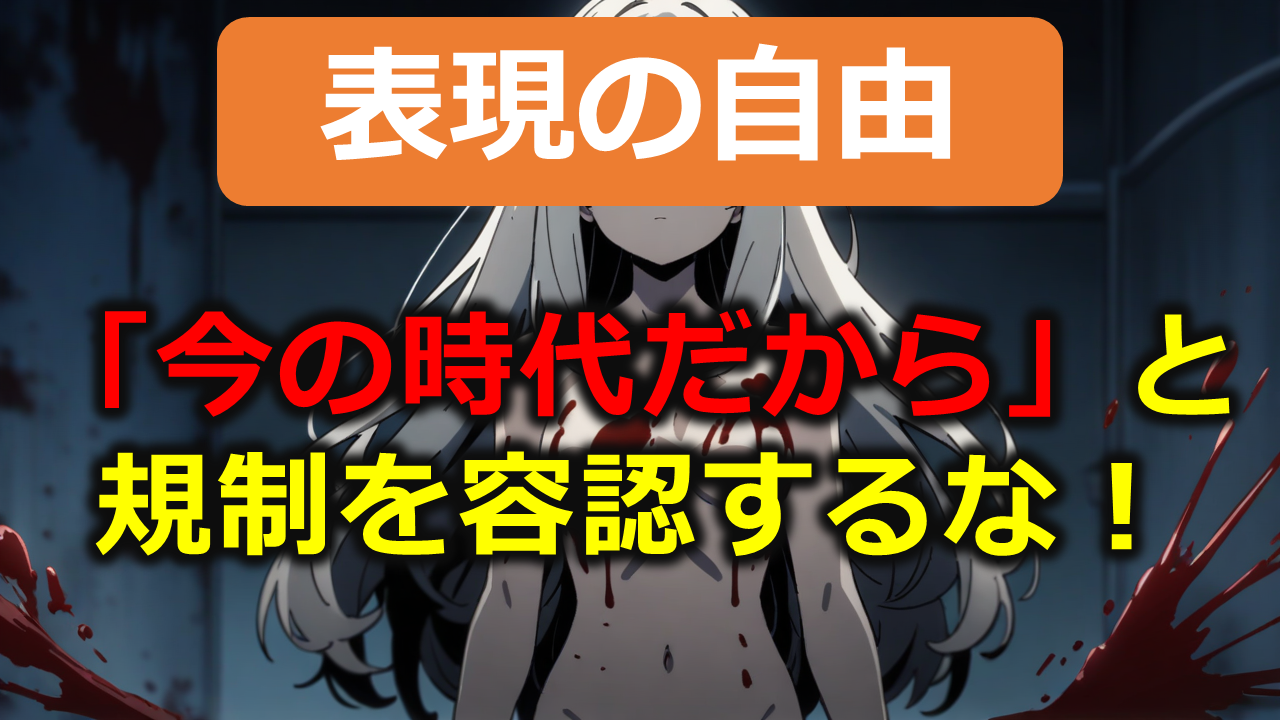はじめに
.png)
どうも! みなため(@MinatameT)です。
最近、次のような言葉狩りをよく見かけるようになりました。
- 死ぬ → ○ぬ、4ぬ、タヒぬ
- 殺す → ○す、56す
- バカ → バ○
- キチガイ → キチ○イ
SNSや動画サイトでのペナルティー(BAN)を回避するために、また、コンプラ意識によって、上記のようなセルフ言葉狩りをしているのはわかっています。
しかし、私はこうした言葉狩りについて、意味がないだけでなく問題がある(有害である)とも考えていますので、その理由を説明していきます。
※これは、プラットフォーム側(YouTubeなどのサイト側)の規制だけでなく、自主的な伏せ字も含みます。
新しい言葉とマナーが生まれる
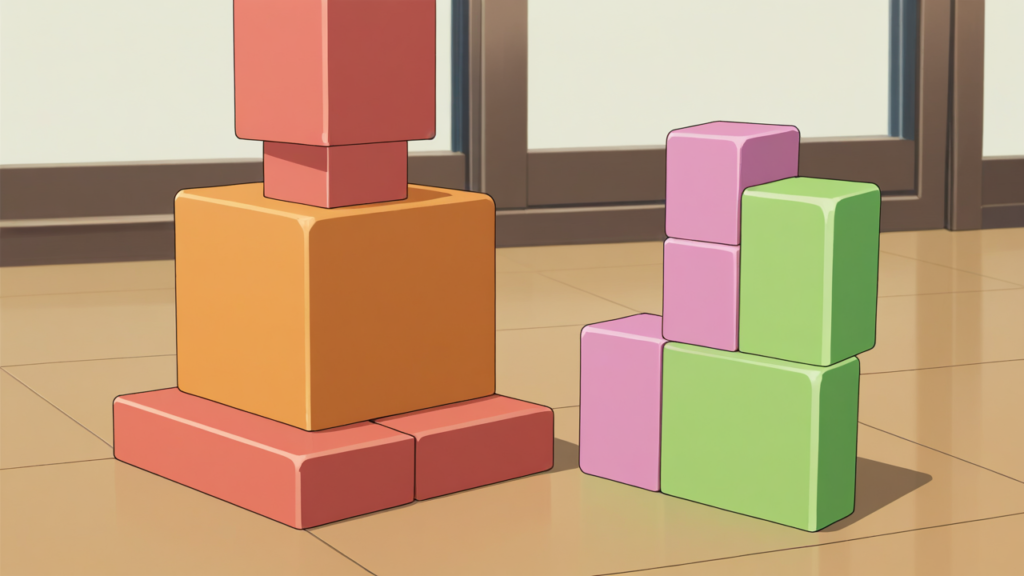
特定の言葉が社会的に使用できない雰囲気になると、別の似たような意味の言葉が使われるか、新しい言葉が使われるようになります。
そして、以前の言葉を使うのはマナー違反とされ、代わりの言葉を使うのが望ましいという風潮になります。
これは本当に面倒くさいです。
どう面倒くさいのかといいますと、こちらは攻撃的な意味でその言葉を使っていなくても、「そんな言葉を使うなんてひどいやつだ!」とか「マナー違反だぞ!」とか、しょうもない文句を言われる可能性がある点です。
ここで気づいていただきたいのは、どれだけ工夫してきれいな言葉を使っていようが誹謗中傷をする行為がダメなのですから、使っている言葉だけで善悪を判断するのは適切ではありません。
いわゆる放送禁止用語も同じ理由で、おかしなルールだと判断しています。
しかも、新しい言葉も次第に攻撃的な意味で使用されるようになっていくと、その言葉もまた封印の対象となるでしょうから「きり」がありません。
だから、言葉狩りは意味がないのです。
まさに形式主義の権化です。
言葉は表現方法の1つ

人間は言葉、表情、ジェスチャーなどの表現を組み合わせてコミュニケーションをとりますが、言葉はその表現方法の1つです。
言葉を封じるということは、私たちの表現の幅を狭めることになりますし、気持ちや事実を伝える効率が悪くなります。
「伏せ字をしても意味が伝わるなら大丈夫でしょ? 文脈でわかるでしょ?」と思うかもしれませんが、私たちの表現の自由が奪われていき、それが当たり前になるという状況に危機感を覚える必要があります。
「自由を奪われている」という自覚をもちましょう。
無意識レベルでの言論統制が進む

伏せ字をするなどして、特定の言葉(表現)を封じることが常識になっていくと、その表現を奪われていることにすら気付けないような人が増えるものです。
ええ、人間とは愚かなものです……(笑)。
そして、多くの人が「これは伏せ字にするやつ」と、特定の言葉を自主的に封じるようになり、表現の自由が抑圧された「おきれいな社会」になっていくわけです。
「不適切な表現が自主規制される社会は素晴らしいはず」と一瞬思うかもしれませんが、その規制の風潮がどんどんエスカレートし、社会が全体主義に染まっていく可能性を考慮しなければなりません。
実際に、昭和の時代と比べると、令和の時代はテレビ番組や漫画での「表現の許容範囲」が狭くなっているという事実があります。
これはエンタメ業界の自主規制がエスカレートし、それに世間の常識が適合していった結果といえるでしょう。
つまり、息苦しく不寛容な社会に変化してしまったということです。
「昔であれば叩かれなかったのに、今の時代はこれを言うとすぐに叩かれる」という感じですね。
これは民主主義社会のあるべき姿なのでしょうか?
厳しい意見かもしれませんが、自主規制に協力した人たちは猛省しなければなりません。
そして、私たちもそういった失敗の歴史から学び、同じような失敗を繰り返さないように意識する必要があります。
おわりに
「自主規制される状況を無意識で受け入れている人が大半なのであれば、それで問題ないのでは?」という意見もあるでしょうが、私は人間らしさには「自由」が必須要素であると考えています。
大げさに聞こえるかもしれませんが、人間らしさが奪われているという状況に人間が気付けないのは非常にヤバいです。
しかも前述のとおり、言葉狩りは形だけで意味のないことです。
SNSや電子掲示板を見たらわかるとおり、特定の言葉を封じたところで人間の攻撃性は低下しませんよね。
また、言葉狩りや厳しい校則などの「意味のないことをやらせる」というのは、人間の主体性や自己肯定感を奪う方法として知られていますから、その点も危惧しています。
私たちの人間らしさを守っていくためにも、無意味な言葉狩りに協力せず、表現の自由を積極的に行使していき、言葉を自由に使える社会へと変化させていきましょう!
おまけ:その言葉で傷つく人がいるかも?
自主的に言葉狩りをしている人の中には、いわゆる差別用語(ホモやクロンボなど)によって実際に傷つく人に配慮している場合もあるかもしれません。
しかし、他人から言われて不快になる言葉は人によって違っており、配慮していたらきりがありません。
しかも、そうやって配慮をする人が続出するから「その配慮をするのが普通なんだ」という風潮になっていき、言葉狩りが加速していくということを忘れてはなりません。
傷つけない言葉遣いを意識するのは素晴らしいことですが、過剰な配慮は社会を不寛容化させてしまいます。
「自由で寛容な社会を実現するためには、社会の不寛容さだけには寛容になってはならない」という、矛盾的な意識が必要なのです。
これを「寛容のパラドックス」といいます。